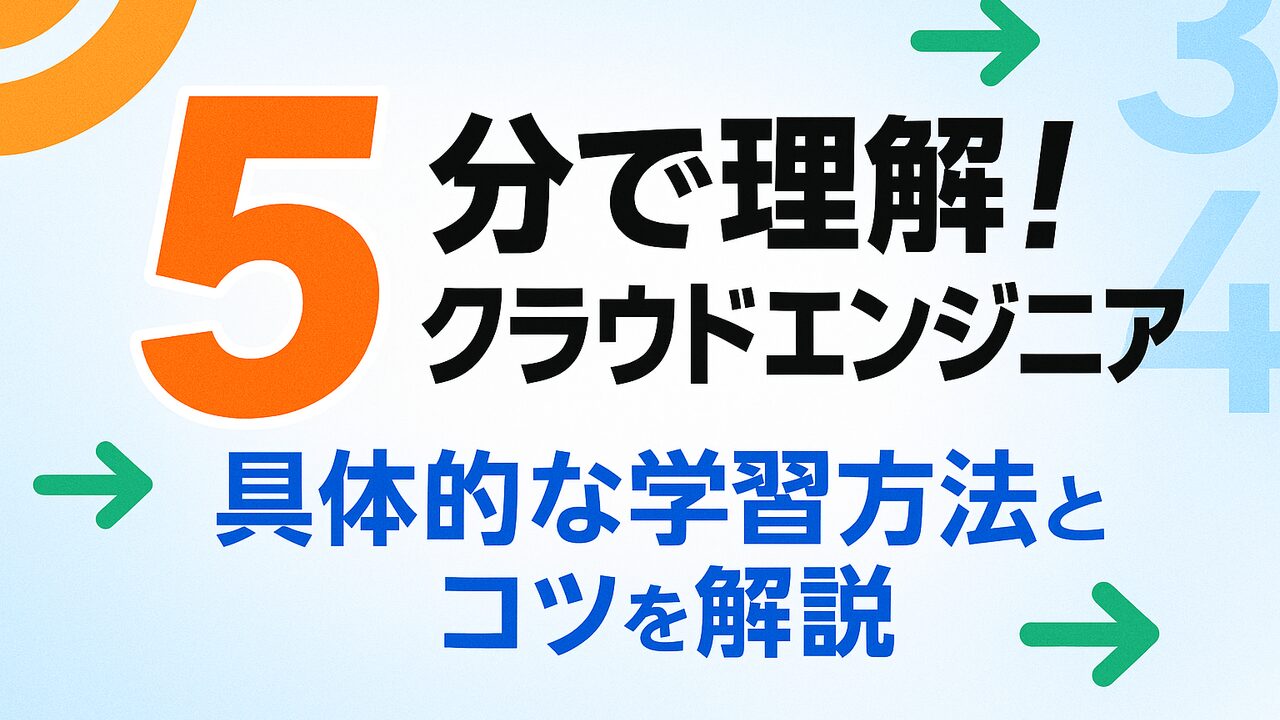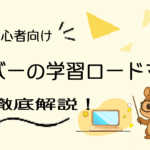「インフラエンジニアとして何から学べばいいのか分からない」
「将来のキャリアや資格取得の目標をどう立てればよいか迷っている」
IT業界の中でも、サーバーやネットワーク、データベース、セキュリティといった基盤を扱うインフラエンジニアは、幅広い知識が求められる一方で、需要が高く、安定したキャリアを築きやすい職種です。
本記事では、学習を始める前に考えておくべきことから、必要な知識、資格取得を目指すメリットまでわかりやすく解説していきます。
学習前に考えておくべきこと
インフラエンジニアを目指して学習を始める前に、まずは仕事の全体像を理解しておくことが重要です。
また、学習に使える時間や予算をあらかじめ確認しておくと、無理のない計画を立てやすくなります。
1. インフラエンジニアとはなにか知っておく
インフラエンジニアとは、ITサービスを支える「基盤(インフラ)」を設計・構築・運用する専門職です。
ITインフラとは、アプリケーションを支えるサーバー、拠点やクラウドを結ぶネットワーク、データを守り活用するデータベース、外部からの攻撃や内部の不正を防ぐセキュリティなど、アプリケーションが動作するために必要不可欠な土台です。
もしインフラが不安定であれば、どれだけ優れたアプリケーションでも正常に動作することはできません。
ECサイトを例にインフラエンジニアの役割を解説
たとえばECサイトを例にすると、このようなリスクを防ぐのがインフラエンジニアの役割です。
- サーバーがダウンすれば商品ページが表示されない
- ネットワークに障害があれば決済が停止する
- データベースが壊れれば在庫情報が消える
- セキュリティが甘ければ個人情報が漏洩する
まさに「縁の下の力持ち」であり、トラブルが起こった際には真っ先に頼られる存在でもあります。
さらに近年はクラウド技術の普及によって、AWSやAzure、GCPといったクラウド基盤を利用する企業が急増し、従来のサーバー運用だけでなく、クラウド上での設計・構築スキルが求められています。
2. どの分野から学ぶべきか考える
インフラの学習範囲は非常に広く、すべてを一度に学ぼうとすると挫折しやすくなります。だからこそ、まずは優先順位をつけて取り組むことが大切です。その際には「自分が将来どんなエンジニアになりたいか」をぼんやりと考えておくと方向性が定まりやすくなります。
たとえば、AI分野に強くなりたいならサーバーやデータ処理の基礎、企業インフラを支える仕事をしたいならサーバー管理やセキュリティ、通信の専門性を高めたいならネットワークの知識が軸になります。
まずは Linuxサーバーの基本操作 や ネットワークの仕組み から学ぶのがおすすめです。
これらはインフラの土台であり、どの分野を目指すにしても必須スキルです。その後、データベースやセキュリティ、クラウドの学習に広げていくと、知識がつながりやすく、資格や実務でも応用しやすくなります。
3. 学習に使える時間や予算を確認する
未経験からインフラエンジニアを目指す場合、学習にかかる時間は数百時間単位です。
- 平日は1日1~2時間
- 休日は3~5時間
といったペースで取り組むと、半年から1年で資格取得レベルに到達できます。ただし、働きながらの学習であれば、スケジュールの工夫が欠かせません。
また、教材やスクールにかかる費用もあらかじめ把握しておきましょう。参考書は1冊3,000円前後、資格試験は1万円~3万円程度、スクールは数十万円の投資が必要です。無料の動画や学習サイトから始め、徐々に有料教材に切り替えると無理なく継続できます。
インフラエンジニアに必要な知識

インフラエンジニアとして活躍するためには、幅広い知識をバランスよく身につけることが大切です。サーバー、ネットワーク、データベース、セキュリティを段階的に学ぶことで、安定したインフラ環境を支えられるエンジニアへ成長できます。
1. サーバーの基礎知識
サーバーはインフラの中心です。学習はまず Linux から始めましょう。覚えておきたいポイントは次のとおりです。
- ユーザーとグループ、権限の仕組み
- サービスとプロセスの違い、ログの確認方法
- パッケージ管理、設定ファイル、定期実行の仕組み
- Webサーバーの役割(HTTPS、リバースプロキシ、キャッシュなど)
- 仮想化の基礎(ハイパーバイザー、複数OSの稼働)
- コンテナの基本(イメージ、ボリューム、ネットワーク)
特にLinuxの基本操作(コマンド、ユーザー管理、ファイル操作など)は必須です。さらに、VMwareやKVMといった仮想化技術や、クラウドでのサーバー構築も学んでおくと実務で役立ちます。
2. ネットワーク知識
ネットワークはインフラの「道」にあたる部分です。学習すべきポイントは以下の通りです。
- IPアドレスとMACアドレス、ARPの役割
- スイッチングとルーティングの違い
- NATやポートフォワーディングの仕組み
- DNSとTTL
- HTTP、TLSの基本動作
- クラウド特有の概念(VPC、サブネット、ルートテーブル、セキュリティグループ)
- 監視と運用(メトリクス・ログ・トレース、アラート設計)
IPアドレス、サブネットマスク、ルーティング、DNSなどの基本概念は必ず理解しておきましょう。加えて、スイッチやルーターの仕組み、ファイアウォールなどのセキュリティ機器の役割を学ぶことで、ネットワークトラブルにも対応できるようになります。
3. データベース知識
データベースはアプリケーションの「情報を保存・管理する倉庫」のような存在です。理解しておくべき点は以下の通りです。
- 正規化と非正規化
- インデックスの使い方と注意点
- トランザクションとロック
- バックアップと復旧手順
- レプリケーション、フェイルオーバー
- SQLの実行計画
- クラウドのマネージドRDBの特徴
代表的なRDBMSとしてはMySQLやPostgreSQLがあり、SQLの基礎文法を理解しておくと良いでしょう。また、バックアップ・リストア手順やパフォーマンスチューニングといった運用面の知識も重要です。
4. セキュリティ知識
セキュリティはインフラ全体を支える「背骨」とも考えられます。学ぶべき内容は以下の通りです。
- 最小権限の原則、多要素認証
- 鍵と証明書の管理
- パッチ適用、脆弱性情報の把握
- 通信の暗号化、ログの保全
- インシデント対応、変更管理
- 責任共有モデル(クラウド特有の考え方)
- 権限の棚卸し、アラートの調整
インフラエンジニアはシステムの安全を守る責任も負っています。特に最近はサイバー攻撃の高度化が進んでおり、セキュリティを軽視するとシステム全体が危険にさらされます。資格学習と並行して、セキュリティの基礎を押さえておきましょう。
資格取得を目指して学習をするのがおすすめ

資格取得を目標に学習を進めることは、キャリアアップやスキル習得に大きな効果があります。ここでは、資格学習のメリットと注意点を解説します。
目標や学習スケジュールが立てやすい
資格試験は学習の明確なゴールになります。たとえば「3か月後に基本情報技術者試験」「半年後にCCNA」といった形で期限を設定することで、学習計画を立てやすくなります。
ゴールが明確であれば、学習の進捗管理もしやすく、モチベーション維持にもつながります。
モチベーションを維持しやすい
資格取得は「合格」というわかりやすい成果が得られるため、学習を継続する大きなモチベーションになります。
また、周囲からの評価も得やすく、転職や案件獲得の際に強みとしてアピール可能です。「試験日まであと少し」と思えば自然と勉強に集中できるので、未経験者ほど資格学習を軸にするのがおすすめです。
資格費用がかかることが懸念点
資格試験には受験費用が発生します。たとえばCCNAは約4万円、AWS認定資格は1万5千円前後かかります。繰り返し受験するとコストが大きくなるため、計画的に受験することが重要です。
ただし、長期的に見れば資格はキャリアアップの投資であり、年収アップや転職成功によって十分に回収できる可能性があります。
おすすめの学習方法3選
効率的にスキルを身につけるためには、自分の学習スタイルに合った方法を選ぶことが大切です。ここでは、それぞれの特徴と活用のポイントを紹介します。
1. 【無料コンテンツ】youtube・学習サイト
YouTubeには初心者向けのインフラ解説動画が数多く存在し、無料で体系的に学べる教材も増えています。また、QiitaやZennといった技術ブログも参考になります。無料で始められるため、学習の最初の一歩として最適です。ただし、断片的な情報が多いため、体系立てて学ぶ工夫が必要です。
2. 【本】参考書や問題集
体系的に学ぶなら書籍が最もおすすめです。Linuxの知識やネットワークスペシャリストの参考書、資格試験対策本などを活用すると効率的に学べます。特に問題集を繰り返し解くことで、自分の理解度を確認しながら知識を定着させられます。
3. ITスクールで学ぶ
独学が難しい人や短期間でスキルを習得したい人にはITスクールがおすすめです。講師から直接フィードバックを受けられるため、効率的に学習を進められます。
また、転職サポートや企業紹介を行っているスクールもあり、未経験からのキャリアチェンジに役立ちます。ただし、費用は高額になるため、投資と回収のバランスを考える必要があります。
未経験者向けの具体的な学習方法
未経験からITスキルを身につけるためには、段階的に学習を進めることが重要です。下記で具体的な学習方法をご紹介します。
参考書か動画で基礎を学ぶ
まず「Linuxの基本操作」「ネットワークの基礎概念」といった初歩を参考書や動画で学びましょう。初心者にとって難しい部分もありますが、図解入りの教材を選べば理解がスムーズになります。
手を動かしながら学ぶ
インフラは実際に操作しなければ身につきません。仮想環境を構築してサーバーを立ち上げたり、クラウドの無料枠を使ってAWS環境を触ったりと、手を動かす学習を心がけましょう。単に知識を覚えるのではなく、実際に操作することで理解が深まります。
ドットインストール、Progate、CloudLicenseで資格対策
プログラミング学習サービスとして有名なドットインストールやProgateは、インフラ分野の基礎理解にも役立ちます。
また、資格対策特化型サービスのCloudLicenseを使えば、AWSやAzureの試験範囲を効率的に学べます。短時間で要点を整理できるため、独学に不安がある人におすすめです。
資格を取得する
最終的には資格取得を目指すことで学習に区切りをつけられます。
初心者ならITパスポートや基本情報技術者試験、ネットワーク基礎を固めたいならCCNA、クラウドを扱いたいならAWS認定資格といったように、目標を決めて取り組むと良いでしょう。
資格は実務経験がない未経験者にとって大きな武器になります。
まとめ
未経験からインフラエンジニアを目指すには、学習の順序を意識しながら計画的に取り組むことが大切です。サーバー・ネットワーク・データベース・セキュリティといった基礎を押さえたうえで、資格取得を目標に据えると学習がスムーズになります。学習方法は無料動画や参考書、ITスクールなど多様ですが、重要なのは「自分に合った方法を選び、継続すること」です。実際に手を動かしながら学び、資格を取得すれば、未経験からでも確実にインフラエンジニアとしてのキャリアを切り開けます。