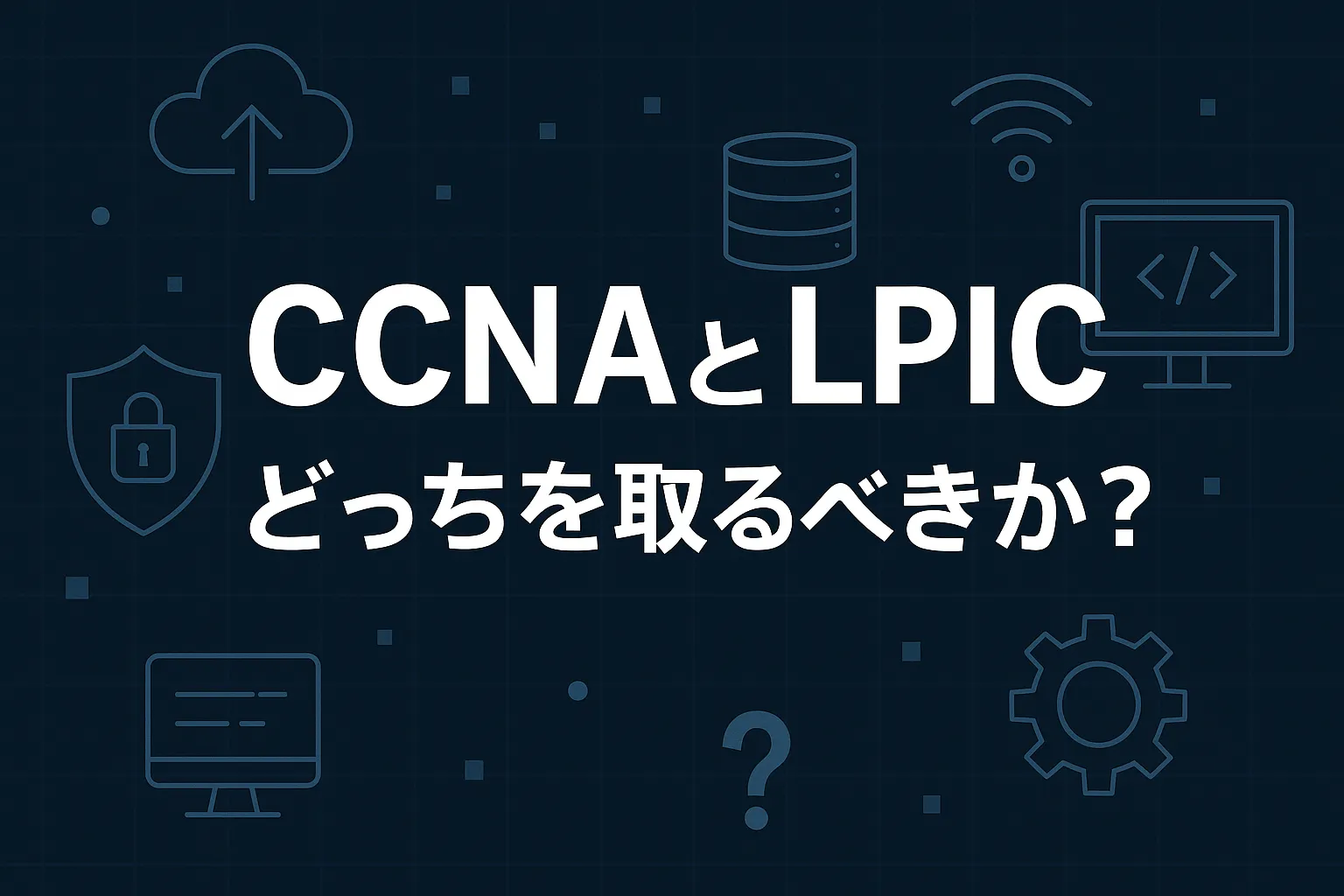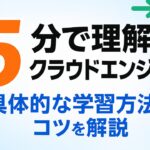ネットワークやサーバーを扱うインフラエンジニアを目指す際、まず候補に挙がるのが「CCNA」と「LPIC」です。しかし、どちらを先に学ぶべきか迷う方も多いでしょう。
本記事では、現役エンジニアの視点からCCNAとLPICの違い、取得メリット、就職市場での評価、効率的な勉強法までわかりやすく解説します。
CCNAとLPICどっちを取るべきか?
CCNAとLPICはどちらもインフラエンジニアを目指すうえで有効な資格ですが、キャリアの方向性によって優先すべき資格は異なります。
企業ネットワークやルーター・スイッチの設定など、ネットワーク構築・運用を中心にしたいならCCNAがおすすめです。
一方、Linuxサーバーの操作やユーザー管理、シェル操作など、サーバー構築・運用を重視するならLPICから学び始めると効率的です。
さらに、AWSやAzureといったクラウド環境では、ネットワークとサーバーの両方の知識が求められるケースが増加しています。
CCNAではVLANやルーティング、LPICではLinuxコマンドや権限設定など、実務でそのまま使える知識が得られるのも大きな魅力です。
まずは興味や目指す職種に合わせて一方を選びつつ、将来的には両方の知識を習得することで、クラウド時代に対応できるエンジニアを目指せます。
CCNAとLPICの基本情報
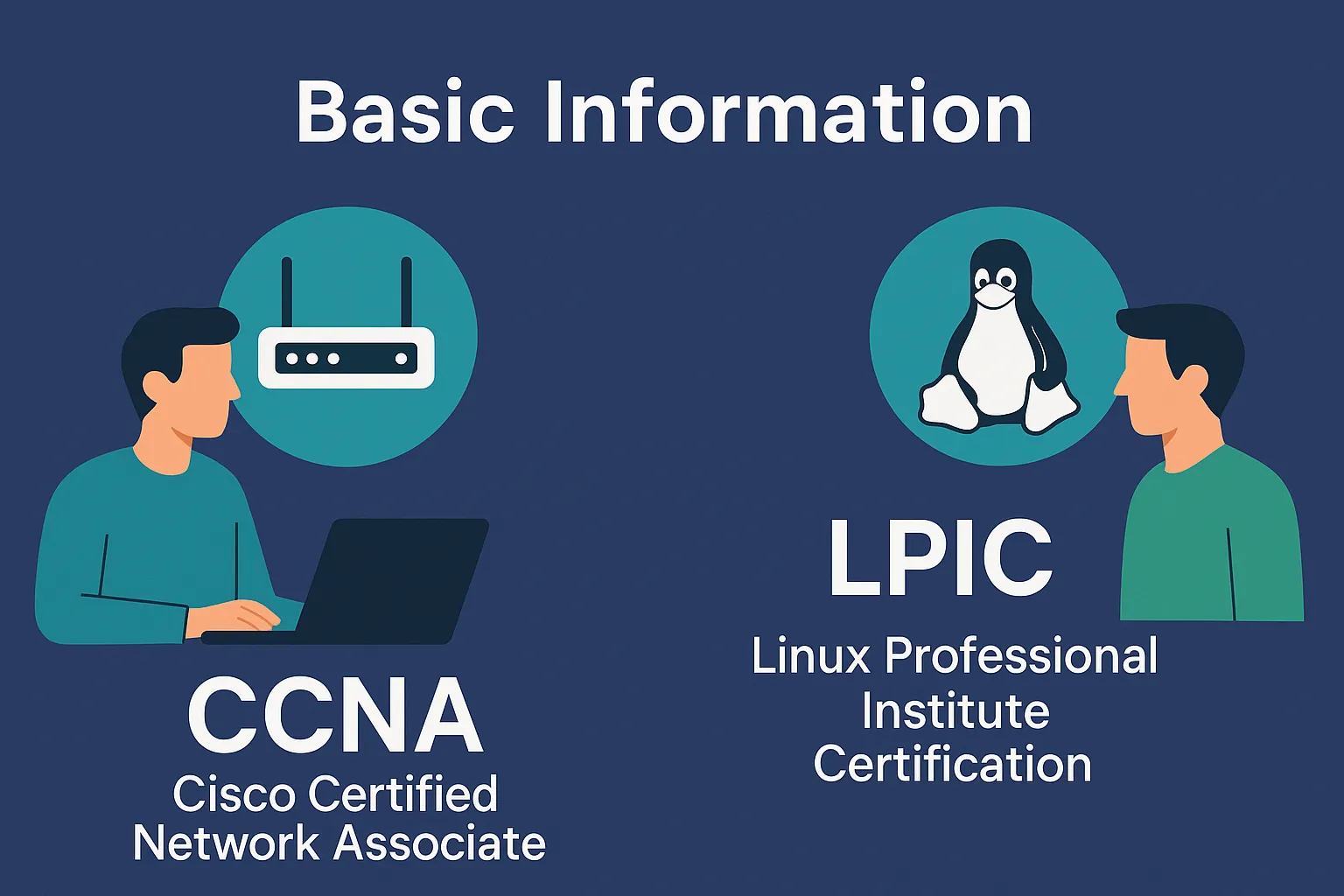
CCNAとLPICはどちらもインフラエンジニアを目指すうえで人気の資格ですが、扱う技術領域や特徴が異なります。
ここでは、それぞれの資格の概要を整理し、どのようなスキルが身につくのかを解説します。
CCNA(Cisco Certified Network Associate)とは
CCNAは、ネットワーク機器で世界的シェアを持つCisco社が提供する国際資格で、ネットワーク構築・運用に関する基礎知識を証明できる資格です。
試験では、IPアドレス設計、ルーティング、スイッチング、VLAN設定、ネットワークセキュリティなど、ネットワーク全般の実務に直結する内容を幅広く学びます。
試験は1回で完結するため、計画的に学習すれば未経験者でも合格を目指しやすい点が特徴です。
さらに、CCNAで得られる知識はオンプレミス環境だけでなく、AWSやAzureなどクラウドサービスのネットワーク設定にも応用可能です。
CCNAは多くの企業で認知度が高く、ネットワークエンジニアやインフラエンジニアとしてキャリアをスタートしたい方に特におすすめの資格です。
CCNA(Cisco Certified Network Associate)とは
LPICは、Linux技術者認定資格として世界的に認知されている国際資格で、サーバー構築・運用管理に必要な知識を証明できる資格です。
試験範囲は、Linuxコマンド操作、ユーザー管理、ファイルシステム、シェルスクリプト、ネットワーク設定など多岐にわたります。
実際の業務で必要となる知識が多く含まれており、サーバーエンジニアやクラウドエンジニアを目指す方に特に有効です。
LPICはレベル制が採用されており、初学者向けの「LPIC-1」から始まり、「LPIC-2」「LPIC-3」と段階的にスキルを高めていけるのが特徴です。
また、AWSやAzureなどのクラウドサービスでもLinuxベースのサーバーが多く採用されているため、クラウド環境での業務を目指す方にも役立つ資格です。
CCNAとLPICの違いを徹底比較
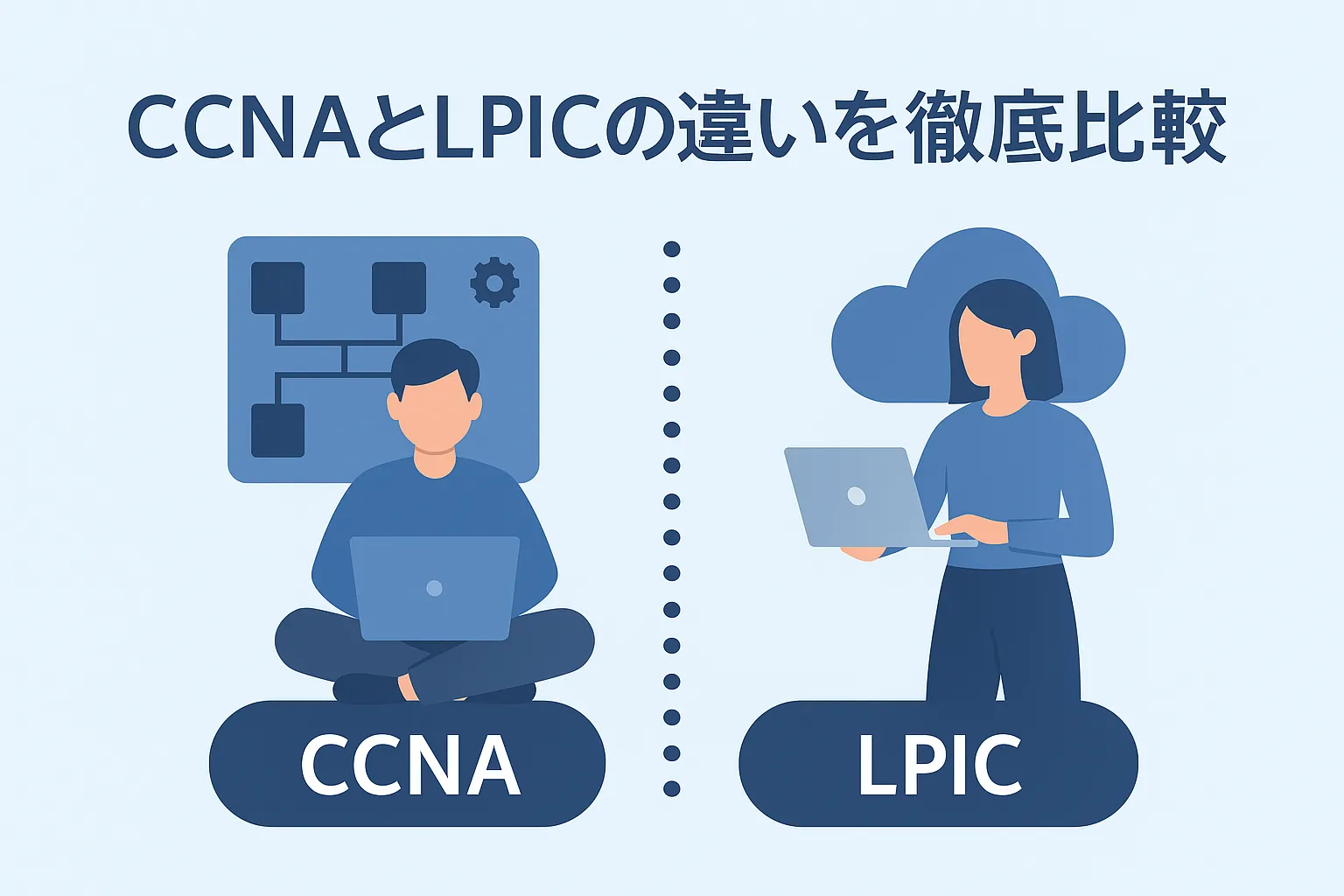
CCNAとLPICはどちらもインフラエンジニア向けの資格ですが、扱う技術や学習内容、試験形式、キャリアへの影響は大きく異なります。
ここでは4つの観点から詳しく比較します。
① 学習内容の違い
| 項目 | CCNA | LPIC |
|---|---|---|
| 学習分野 | ネットワーク全般 | Linuxサーバ管理 |
| 具体的な範囲 | ルーター・スイッチ設定、VLAN構築、IPアドレス設計、ルーティング、ネットワークセキュリティ | Linuxコマンド、ユーザー管理、シェルスクリプト、パッケージ管理、ネットワーク設定 |
| 主な目的 | ネットワークの設計・構築・運用 | サーバー環境の構築・運用・管理 |
| 活かせる職種 | ネットワークエンジニア、インフラエンジニア | サーバーエンジニア、クラウドエンジニア |
CCNAは、ネットワークに関する知識を体系的に学べる資格で、企業ネットワークの設計や運用、障害対応など幅広い業務に直結します。
ルーティングやVLAN設定など実務で頻繁に使うスキルを習得できるのが特徴です。
LPICはLinuxサーバーの構築・運用・管理に特化した資格で、Linuxコマンド操作やユーザー管理、シェルスクリプト作成など、サーバー管理者に必要な実践的スキルを身につけられます。
つまり、CCNA=ネットワーク全般、LPIC=サーバー管理という役割の違いを理解することが、資格選びの第一歩になります。
② 試験難易度の違い
CCNAは1回の試験で完結しますが、出題範囲が広いため、効率的な学習計画が重要です。
ネットワーク基礎からルーティング、スイッチング、セキュリティまで幅広い知識が求められ、未経験者の場合は100〜150時間程度の学習が目安です。
LPICはレベル制で、初学者は「LPIC-1」からスタートします。
LPIC-1は2つの試験(101・102)に合格する必要があり、Linuxコマンドやユーザー管理、ネットワーク設定などを重点的に学びます。
範囲はCCNAより狭いものの、コマンド操作など実務的な内容が多いため、手を動かしながら学習することが重要です。
③ 資格の有効期限
| 資格名 | 有効期限 | 更新方法 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| CCNA | 3年 | 再受験または上位資格取得 | 技術進化に合わせた最新知識の更新が必要 |
| LPIC | 5年 | 再受験または上位資格取得 | 上位資格取得で下位資格も延長可能 |
CCNAは取得日から3年間の有効期限があり、期限が切れる前に再受験するか上位資格へステップアップすることで認定を維持できます。
ネットワーク技術は進化が早いため、最新知識を更新する目的で有効期限が設定されています。
LPICは一部を除き5年間の有効期限があり、更新には再試験が必要です。
ただし、上位資格を取得すると下位資格も自動的に延長される仕組みがあるため、長期的なキャリア設計がしやすい点が特徴です。
キャリアを考える場合、短期で更新が必要なCCNAか、比較的長く有効なLPICかを意識することが重要です。
④ 就職・転職市場での評価
CCNAはネットワークエンジニアやインフラエンジニアを目指す人にとって、非常に評価が高い資格です。
特に企業のネットワーク構築・運用に携わる求人では、「CCNA取得者歓迎」や「取得済みが望ましい」と明記されるケースが多く、即戦力アピールに直結します。
LPICはLinuxを扱うサーバーエンジニアやクラウド環境の運用者に評価される傾向があります。
AWSやGCPなどクラウドサービスの普及に伴い、Linuxスキルの重要性は高まっており、LPIC取得者は今後も需要が拡大する見込みです。
どちらの資格もITインフラ分野での評価は高いですが、志望職種や企業の環境に合わせた選択が重要です。
どちらを先に取るべきか?おすすめの選び方

CCNAとLPICは学習範囲が異なるため、目指すキャリアに合わせて優先順位を決めることが重要です。
ネットワーク寄りか、サーバー寄りかで最適な資格が変わります。
ネットワークエンジニア志望ならCCNA
ネットワークエンジニアを目指す場合、まず取得を検討すべきはCCNAです。
CCNAでは、ルーティング、スイッチング、VLAN、サブネットなど、企業ネットワークを構築・運用するための基礎知識を体系的に学べます。
特にCisco製品は国内外で高いシェアを誇るため、実務でもそのまま役立つ知識が多い点が強みです。
また、ネットワーク機器の設定やトラブルシューティング能力を客観的に証明できるため、未経験からインフラエンジニアを目指す方にも有利です。
転職市場でも評価が高く、将来的にクラウドやセキュリティ分野へ進む際の土台にもなります。
サーバー・クラウド志望ならLPIC
サーバー構築やクラウド運用を目指す場合は、LPIC(Linux技術者認定資格)の取得がおすすめです。
AWSやGCPなど主要なクラウド環境はLinuxをベースとしており、サーバーの基本操作や権限管理、シェルコマンドなどの知識が必須になります。
LPICでは、OSのインストールからパッケージ管理、ユーザー管理、セキュリティ設定まで体系的に学べるため、クラウドエンジニアやサーバーエンジニアを志望する方に最適です。
さらに、LPICで身につけたスキルは、AWSやAzureのクラウドサービスを扱う際にも応用可能で、マルチクラウド時代に強みとなります。
インフラ全般を目指すならCCNA→LPICの順
ネットワークからサーバー、クラウドまで幅広く扱うインフラエンジニアを目指す場合は、CCNA→LPICの順で学習を進めるのがおすすめです。
まずCCNAでネットワークの基礎を習得すると、IPアドレス設計やルーティング、セキュリティ設定など、インフラの土台となる知識を効率よく身につけられます。
そのうえでLPICを学ぶことで、Linuxサーバーの操作やクラウド運用に必要なスキルを補完できます。
ネットワークとサーバー両方のスキルをバランスよく習得することで、現場で求められる実践的なインフラ運用能力が養われ、キャリアの選択肢が大きく広がります。
将来AWSやAzureを使いたいならLinux知識は欲しい
AWSやAzureなどのクラウドサービスを活用したい場合、Linuxの基礎知識は欠かせません。
クラウド上で構築される多くのサーバーはLinuxベースで動作しており、コマンド操作や権限管理、パッケージ更新などの知識が業務で求められます。
そのため、LPICの学習を通じてLinuxスキルを習得しておくと、クラウド環境の構築・運用がスムーズになります。
また、AWS認定資格やAzure認定資格の試験範囲にもLinux関連の出題があるため、LPICで基礎を固めておくことは資格取得の効率化にもつながります。
クラウドエンジニアを目指すなら、Linux知識を早めに身につけることが重要です。
CCNAとLPICの資格取得メリット

CCNAとLPICは、ネットワークやサーバーの基礎スキルを証明できる資格です。
未経験からIT業界を目指す方はもちろん、クラウド時代のキャリア形成にも役立ち、転職市場でのアピール材料としても有効です。
未経験からでも知識を証明できる
CCNAやLPICは、実務経験がなくてもITインフラの基礎知識を客観的に証明できる資格です。
特に未経験者の場合、採用担当者はスキルを判断する材料が限られているため、資格の有無が評価に直結しやすいです。
体系的に学習することで、ネットワークやLinuxサーバーの基礎を網羅的に理解でき、学習の過程自体がスキルアップにつながります。
結果として、採用時の信頼性を高める有効な手段となります。
クラウド時代でも基礎スキルとして活用可能
AWSやAzureなどのクラウドサービスが主流になった現在でも、CCNAやLPICで学ぶネットワークやLinuxの基礎知識は欠かせません。
クラウド環境でもサーバー構築やネットワーク設計の基本原理は変わらず求められ、トラブルシューティングの際にも役立ちます。
また、クラウド資格学習の前段階として活用できるため、効率的にキャリアを積み上げるための基盤としても価値が高い資格です。
転職活動での書類選考を突破しやすい
ITインフラ分野への転職では、実務経験が浅い場合でも資格が大きなアピールポイントになります。
CCNAはネットワーク、LPICはLinuxサーバー運用の基礎スキルを証明できるため、書類選考で有利に働くケースが多いです。
特に未経験からの転職やキャリアチェンジでは、資格を取得しているだけで学習意欲や基礎力を示せるため、面接に進める可能性が高まります。
CCNA・LPICそれぞれのおすすめ勉強方法
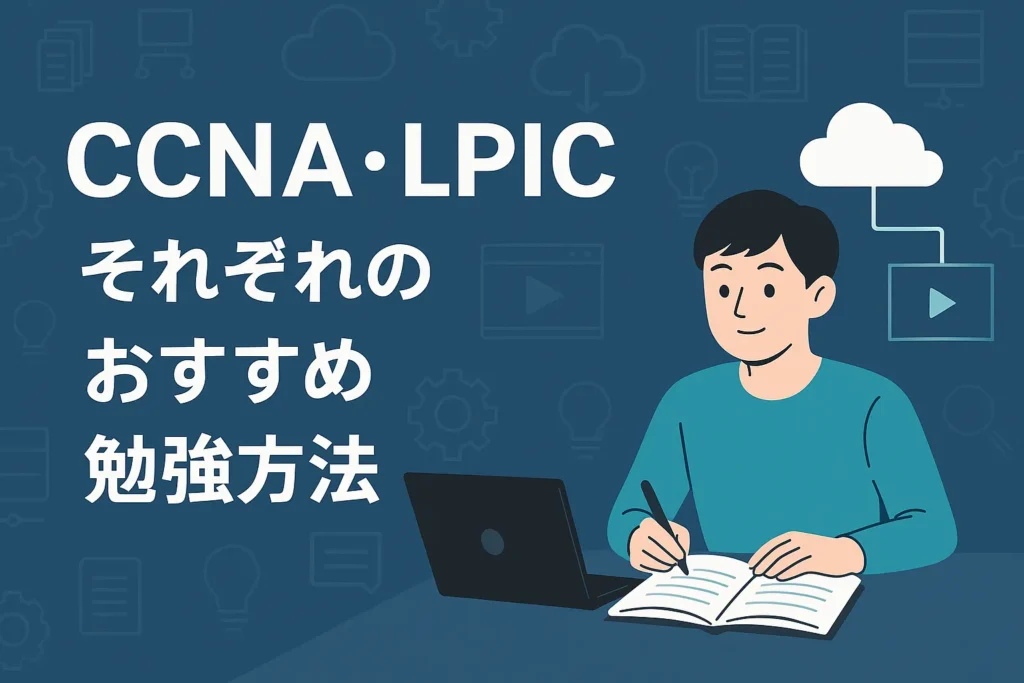
CCNAとLPICでは学習内容や出題範囲が異なるため、効率的に合格するには資格ごとの特徴に合わせた勉強方法が重要です。
ここでは、それぞれに適した学習手順と効果的な対策を解説します。
CCNAの勉強法
CCNAの学習では、まずネットワークの基礎概念をしっかり理解することが重要です。
OSI参照モデル、IPアドレッシング、ルーティング、VLANなどの仕組みをテキストや動画で体系的に学びましょう。
その後、シスコ製ルータやスイッチの設定演習に取り組み、コマンド操作に慣れることが合格の近道です。
実機が用意できない場合は、Cisco Packet Tracer や GNS3 といったシミュレーターを活用すると効率的です。
さらに、過去問や模擬試験を繰り返すことで、出題傾向を把握し弱点を補強できます。
可能であれば、学習コミュニティに参加して最新情報や勉強方法を共有するのも有効です。
LPICの勉強法
LPICの学習では、Linuxの基本操作を実際に手を動かしながら覚えることが重要です。
まずはCentOSやUbuntuなどのLinux環境を自分のPCに構築し、コマンド操作に慣れるところから始めましょう。
特に、ファイル操作・ユーザー管理・権限設定・パッケージ管理などは出題頻度が高いため重点的に学習します。
加えて、シェルスクリプトやプロセス管理、ネットワーク設定などの実践演習も効果的です。
参考書だけでなく、模擬試験や過去問を活用して出題傾向を把握し、弱点を補強しましょう。
また、GitHubやQiitaなどの技術記事で最新情報を取り入れると、より実践的な知識が身に付きます。
演習と座学を並行して進めることで、効率的に合格レベルのスキルが身に付きます。
まとめ
CCNAとLPICは、インフラエンジニアを目指すうえで基盤となる知識を体系的に習得できる資格です。
ネットワークエンジニア志望ならCCNA、サーバー・クラウド志望ならLPICから学習を始めるのがおすすめですが、最終的には両方を取得することでインフラ全体を俯瞰できる力が身につきます。
さらに、AWSやAzureなどクラウド技術の普及により、Linuxやネットワークの知識は今後ますます重要性を増しています。
これらの資格は未経験からでもスキルを証明でき、転職やキャリアアップにおいて強力な武器となるでしょう。