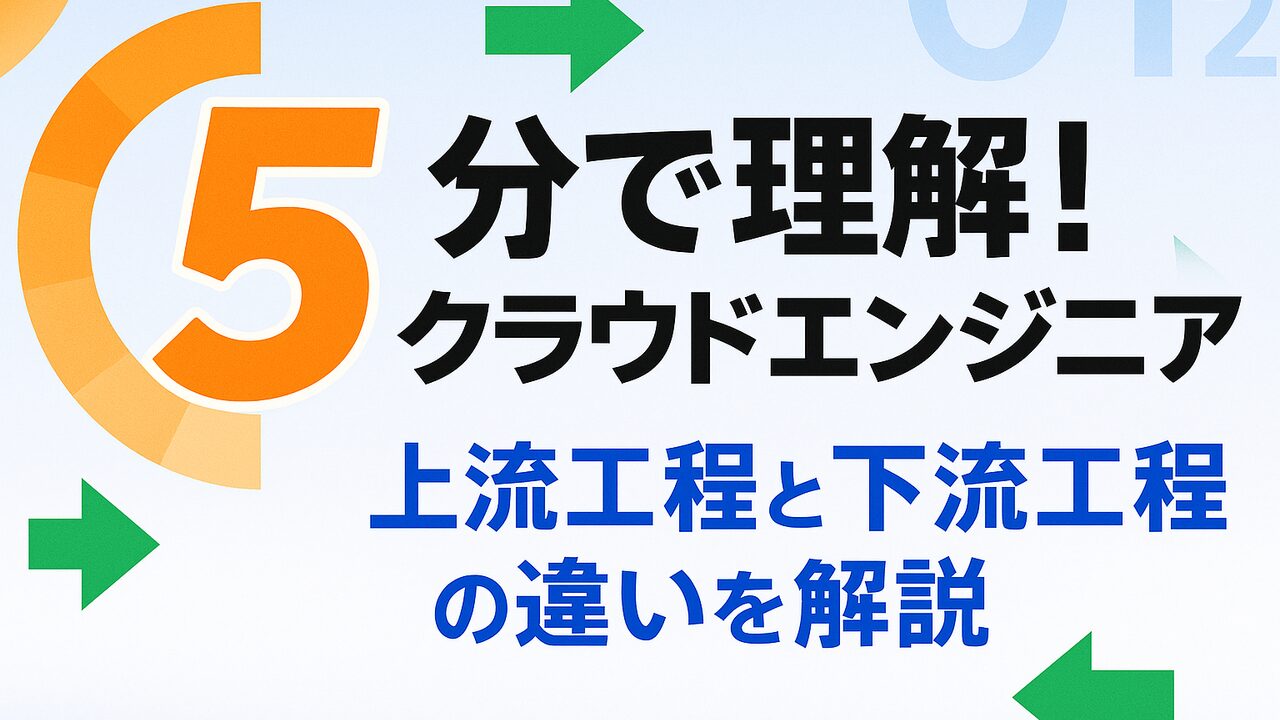「クラウドエンジニアを理解したい」
「未経験からでも効率的にキャリアアップしたい」
クラウドエンジニアは、上流工程と下流工程に分かれ、それぞれで求められる作業やスキルが異なります。
この記事では、両工程の流れや必要スキル、年収の違いをわかりやすく解説し、未経験者でも効率的にキャリアアップできるポイントを整理しています。クラウドエンジニアとしてのキャリア形成を目指す方はぜひ参考にしてください。
上流工程とは?
システム開発における上流工程とは、実際にプログラムを書く前の計画や設計にあたる段階を指します。
具体的には、顧客からの要望を整理して要件定義を行い、システムの目的や機能を明確にします。その後、基本設計や外部設計に進み、システム全体の仕組みや動きを図や文書で表現します。
上流工程はシステム開発の土台となる重要なフェーズであり、この時点で方向性を誤ると後続の工程に大きな影響を及ぼします。そのため、エンジニアだけでなく顧客や関係者との密なコミュニケーションが欠かせません。
特に近年ではアジャイル開発の普及により、仕様を柔軟に見直す動きもありますが、やはり上流工程での合意形成がプロジェクト成功の鍵を握ります。
下流工程とは?
下流工程とは、上流工程で決定した設計をもとにシステムを具体的に作り上げる段階です。
プログラミングによる実装、単体テスト、結合テスト、ユーザー受け入れテストなどを通して、設計通りに動作するかを確認します。完成したシステムは本番環境にリリースされ、運用へ移行します。
下流工程はユーザーが直接触れる部分に直結するため、品質管理が特に重要です。
上流工程に不備があると、手戻りやコスト増加の原因となります。逆に言えば、上流での準備が整っていれば下流工程はスムーズに進み、完成度の高いシステムが効率的に仕上がります。
したがって、上流と下流は切り離せない関係にあり、両者のバランスがシステム開発全体の成功を左右します。
上流工程の流れ
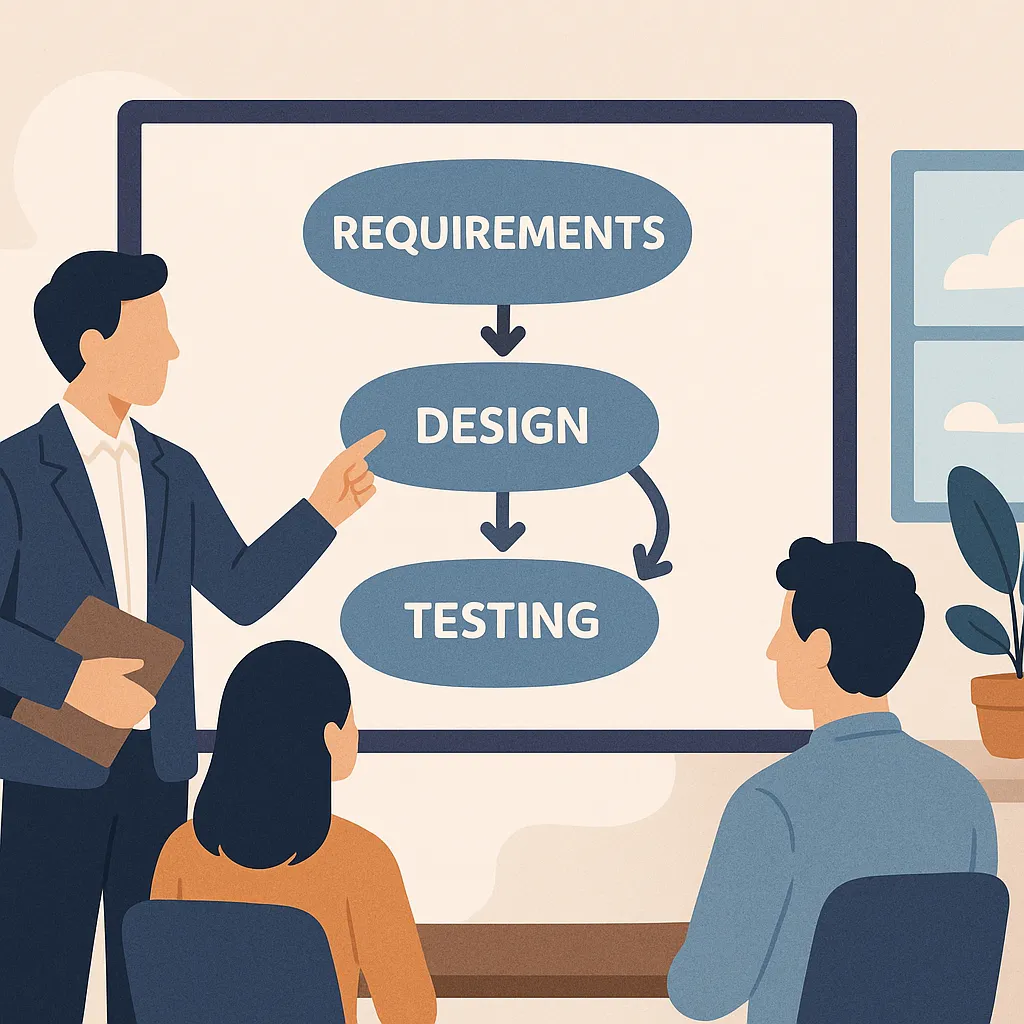
システム開発の上流工程は、プロジェクトの方向性や品質を大きく左右する重要な工程です。主な流れとしては、要件定義、基本設計、詳細設計、そして見積りの4段階です。以下ではそれぞれの工程について解説します。
要件定義
顧客のニーズや課題を明確にし、それをシステムの要件に落とし込む工程です。ここでは機能要件(システムが備えるべき機能)と非機能要件(性能、セキュリティ、運用体制など)が整理されます。要件定義の段階で曖昧さを残すと、後々の設計や開発で齟齬が生じ、追加費用や納期遅延につながります。
逆に、この段階で十分に合意形成ができれば、後の工程はスムーズに進みやすくなります。そのため、顧客とのコミュニケーションが最も重視される工程とも言えます。
基本設計
要件定義で決めた内容をもとに、システムの全体像を描く段階です。
ユーザーインターフェースの構成、画面遷移、データベースの概要など、大まかな仕様を設計します。ここでは、利用者がイメージしやすい形に落とし込むことが大切で、ワイヤーフレームやプロトタイプを用いるケースも多いです。
基本設計が不十分だと、利用者にとって使いにくいシステムになる可能性が高くなります。したがって、開発者だけでなく利用者の視点も取り入れながら設計を進めることが重要です。
詳細設計
基本設計をさらに具体的に落とし込み、プログラム単位で実装できるレベルにまで設計を細分化する工程です。
データベースのテーブル定義、処理手順、外部システムとの連携仕様などがこの段階で決定されます。ここでの設計が正確であればあるほど、下流工程の開発作業が効率的になり、バグや手戻りのリスクを減らすことができます。
また、詳細設計書はプログラマーの作業指針となるため、曖昧さを残さないことが大切です。レビューを重ねることで、品質を担保しながら進めるのが理想的です。
見積り
見積りは、要件定義や設計内容をもとに、プロジェクトに必要な工数や費用を算出する工程です。
人員の稼働時間、システムの規模、利用する技術やツール、テストや運用にかかるコストまでを含めて試算します。見積りは単なる数字合わせではなく、プロジェクトの現実性を左右する重要な指標です。
過小な見積りは品質低下を招き、過大な見積りは顧客に受け入れられにくくなるため、バランス感覚が求められます。また、リスクや不確定要素も加味した現実的な見積りができるかどうかが、プロジェクト成功の分かれ目になります。
下流工程の流れ

システム開発における下流工程では主に開発、テスト、運用・保守、監視といった工程が含まれます。以下にそれぞれの流れを解説します。
開発
プログラマーが詳細設計をもとにソースコードを記述し、システムを実装する工程です。ここでの作業は単にコードを書くことにとどまらず、設計意図を正しく理解し、効率的かつ保守性の高いプログラムを実現することが求められます。
開発段階での小さな判断ミスや仕様の誤解は、後のテストや運用で大きな問題となる可能性があるため、レビューやペアプログラミングなどの品質保証活動も重要です。また、近年ではアジャイル開発が広がり、短いサイクルで実装と確認を繰り返すスタイルも主流になっています。
テスト
開発したシステムが設計通りに動作するかを検証する工程です。単体テストでモジュールごとの動きを確認し、結合テストで複数のモジュールを組み合わせて検証します。さらに総合テストやユーザ受け入れテストを通じて、実運用環境に近い条件での動作を確かめます。
テストは不具合を見つけるためだけでなく、品質を保証するための重要な活動です。特に金融や医療のような高い信頼性が求められる分野では、テスト工程の比重が大きくなります。効率的なテストを行うためには、自動化ツールの活用やテストケースの体系的な設計も欠かせません。
運用・保守
運用はシステムを稼働させ、安定して利用できる状態を維持する工程です。日常的な運用ではユーザー管理やバックアップ、障害対応などが行われます。一方、保守ではソフトウェアの不具合修正や機能改善、法令改正に伴う変更対応などが含まれます。
運用・保守はシステムのライフサイクル全体にわたり継続的に行われるため、最も長期にわたる工程といえます。ここでの対応が遅れるとユーザーの信頼を失い、ビジネスに大きな損失をもたらす可能性があるため、迅速かつ計画的な体制づくりが不可欠です。
監視
システムが正常に稼働しているかを常時チェックする工程です。サーバーやネットワークの稼働状況、ログの異常検知、セキュリティインシデントの監視などが含まれます。監視体制が整っていれば、障害を早期に発見し、被害を最小限に抑えることが可能です。
クラウドサービスの普及により、監視は24時間体制で行われるのが一般的となり、AIや自動化ツールを活用して異常を即座に検知する仕組みも整いつつあります。監視は単なる保守作業ではなく、システムの信頼性を高める基盤であり、ユーザーに安心して利用してもらうための重要な役割を担っています。
上流工程の作業で求められるスキル

システム開発における上流工程では、エンジニアやコンサルタントには高度なスキルが求められます。以下では、代表的なスキルを詳しく解説します。
クライアントの要望を言語化するスキル
上流工程で最も重要なのは、クライアントの抱える課題や要望を正確に言語化する力です。
顧客の多くは専門的なIT知識を持たず、要望を抽象的に伝える傾向があります。そのため、ヒアリングを通じて「顧客が本当に実現したいこと」を引き出し、整理して文書化するスキルが不可欠です。
もしここで誤解や解釈のずれが生じると、完成したシステムが期待に沿わず、再開発や修正が発生します。論理的思考力と同時に、相手の立場に立って理解するコミュニケーション能力も大きな武器となります。
ドキュメント作成・構成図作成能力
上流工程では、要件定義書や基本設計書、システム構成図など、さまざまなドキュメントを作成します。これらの文書は開発チームや運用担当者にとっての指針となるため、曖昧さのない明確な表現と見やすい構成が必要です。
特に構成図は、システム全体の動きを直感的に理解できるようにするための重要なツールです。ドキュメントの品質が高ければ、後工程での認識齟齬や手戻りを防ぐことができ、結果として開発全体の効率向上につながります。そのため、技術力だけでなく、表現力や情報整理能力が求められるのです。
担当分野に関する専門知識
システム開発は幅広い分野にまたがるため、自分が担当する領域に関する深い専門知識が必須です。
例えば、金融システムを手掛ける場合は金融業務の流れを理解し、医療システムであれば診療報酬や患者情報管理の仕組みに精通している必要があります。専門知識が不足していると、要件定義で顧客の言葉を正しく理解できず、適切な設計を行えません。
逆に業務知識を備えていれば、顧客の潜在的な課題を見抜き、より実用的な提案が可能となります。したがって、技術者であると同時に業務の理解者であることが上流工程の担当者には求められます。
セキュリティ・法令を含むITの幅広い知識
近年のシステム開発では、セキュリティ対策や法令遵守が欠かせません。個人情報保護法や著作権法、業界ごとのガイドラインを把握したうえで設計を行う必要があります。
また、クラウド環境の活用が広がる中、ネットワーク構成や認証方式に関する知識も不可欠です。セキュリティ要件を見落とすと、リリース後に重大なインシデントを引き起こしかねません。
さらに、IT技術は日々進化しているため、幅広い分野の最新動向をキャッチアップする継続的な学習姿勢も求められます。幅広いIT知識を背景にした判断力は、上流工程の品質を大きく高める要素となります。
下流工程の作業で求められるスキル
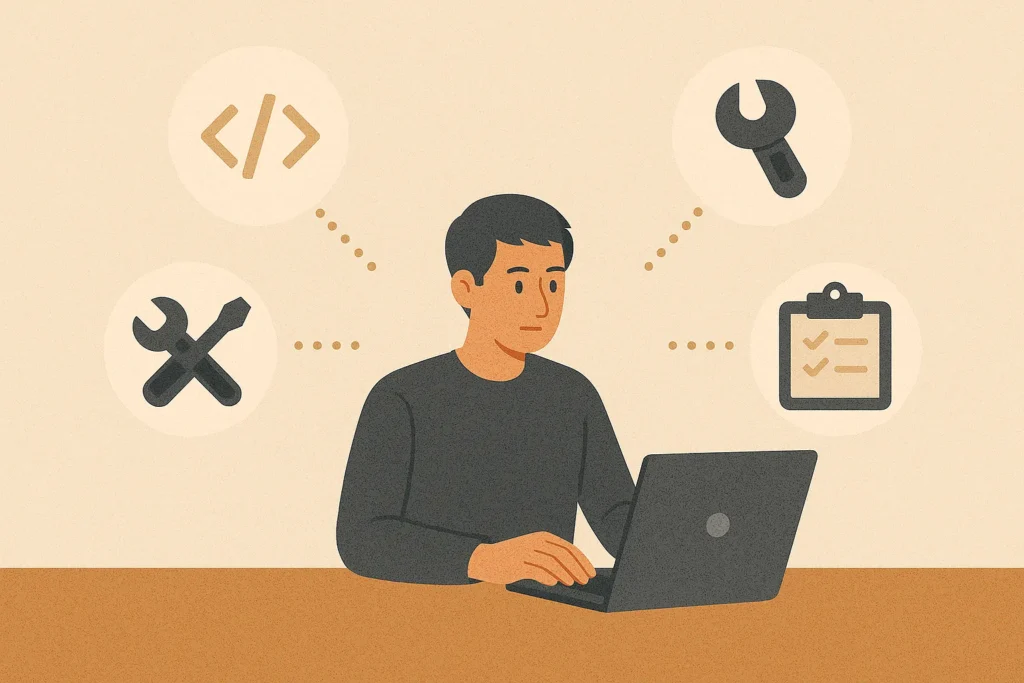
下流工程は、設計をもとにシステムを具体化し、品質を確保する重要な段階です。ここで求められるスキルは実務的であり、効率と正確性が大きなポイントとなります。
基礎的なプログラミング能力
開発工程では、詳細設計を忠実に反映させながらコードを記述する基礎的なプログラミング力が欠かせません。高度なアルゴリズムを生み出すよりも、まずは仕様通りに動作する堅実なプログラムを実装できることが重要です。
また、チーム開発では可読性や保守性を意識したコーディングが求められるため、基本文法の理解に加え、コーディング規約を守る姿勢も必須です。
手順通りにテストを行うスキル
テストでは、設計段階で定義されたテストケースを正確に実施し、結果を客観的に記録する力が求められます。たとえ単純作業に見えても、漏れや思い込みがあると重大な不具合を見逃す可能性があります。
そのため、指示を丁寧に読み解き、手順を厳守する姿勢が不可欠です。さらに、発見した不具合をわかりやすく報告する能力も、下流工程のスキルとして重視されます。
クラウドエンジニア上流工程と下流工程の年収の違い
クラウドエンジニアの年収は、担当する工程によって大きく変わります。業務の難易度や責任範囲の広さが収入に反映されるため、キャリアを考えるうえで理解しておくことが重要です。
上流工程の年収
上流工程を担当するエンジニアは、要件定義や設計といったプロジェクトの方向性を決める重要な役割を担います。
高度な専門知識やコミュニケーション能力が求められ、責任も大きい分、年収は高めです。一般的なクラウドエンジニアの平均年収よりも1〜2割高い水準に位置し、経験豊富な人材であれば700万円以上に到達するケースもあります。
下流工程の年収
下流工程では主にプログラミングやテスト、運用といった実務を担います。基礎的なスキルを着実に発揮することが求められますが、上流工程ほどの裁量は少なく、年収も相対的に抑えられる傾向にあります。
未経験からのキャリアスタートに向いている一方、収入面では500万円前後が目安となり、上流工程との差が見られるのが特徴です。
まとめ
クラウドエンジニアの業務は上流工程と下流工程に分かれ、それぞれ異なるスキルが求められます。この記事では下記をご紹介しました。
- 上流工程、下流工程とは
- それぞれの工程の詳細
- 必要なスキル
- 年収の違い
特徴を理解して自分の適性や目標に合わせてキャリアを積むことで、収入アップやスキル向上につながりますので、ぜひ参考にしてください。