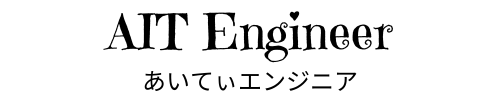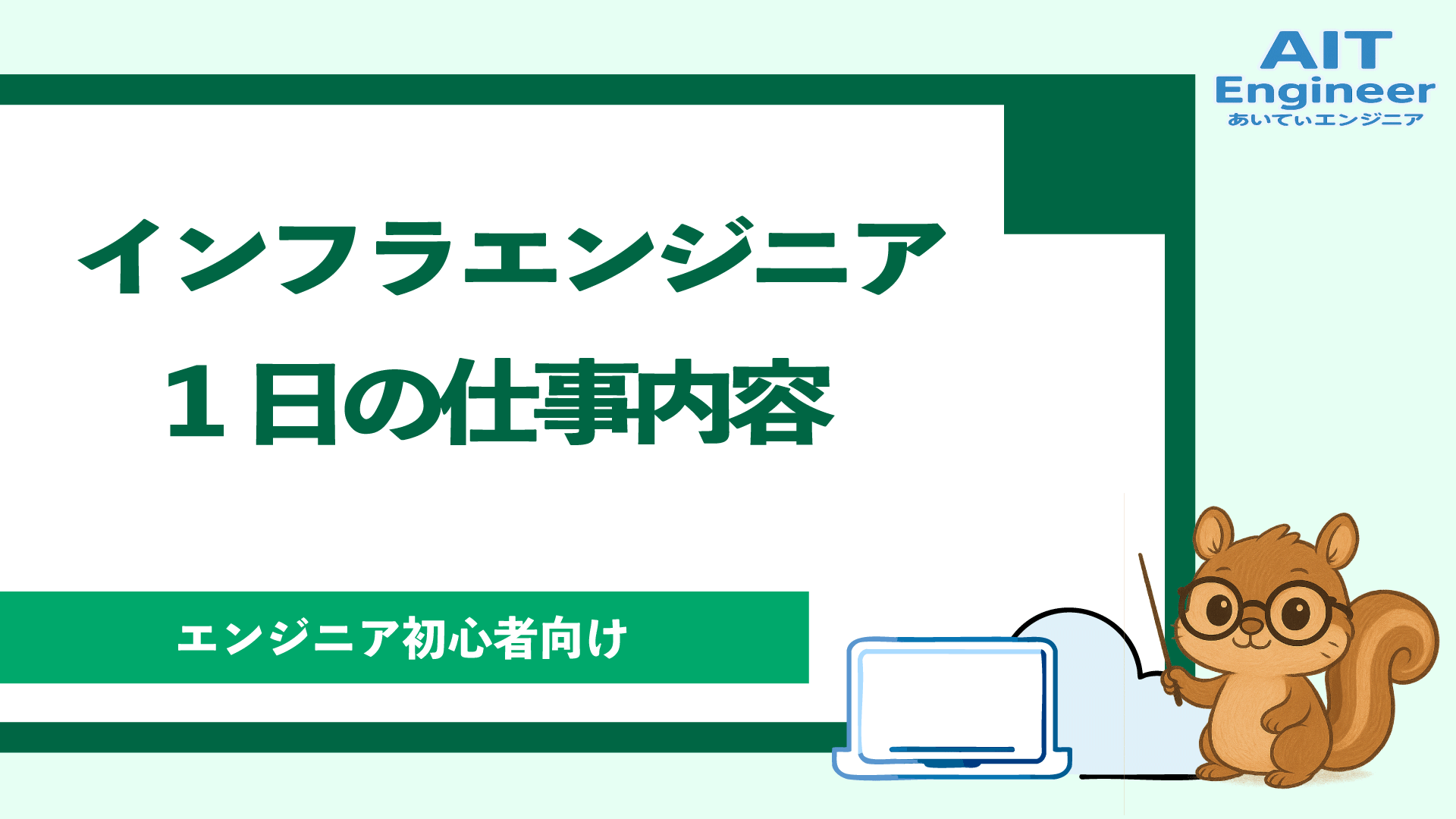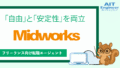インフラエンジニアとは、企業や組織の基盤となるITインフラの設計から構築・整備・保守に従事する職種です。近年では、サーバーのクラウド化が急速に導入されており、インフラエンジニアの需要は高く変化しています。
インフラエンジニアはサーバーエンジニアやネットワークエンジニアに分かれていて、幅広い知識とスキルが求められます。ネットワークやサーバーといったITインフラは、さまざまなシステムを支える重要な役割を担っています。
IT業界でも需要の高い職種でクラウド技術の発展に伴い、技術の範囲が広がりました。しかし、インフラエンジニアを目指す上で具体的にどんな仕事内容なのか・どのようなスキルが求められるのか気になる方が多いはずです。
本記事では、インフラエンジニアの主な仕事内容とツールや技術についてご紹介します。
インフラエンジニアとは?

インフラエンジニアとは、企業のシステムの基盤となるITインフラの設計から構築・整備・保守に従事する職種です。インフラエンジニアは業務範囲が多岐にわたり、担当する技術領域によってサーバーエンジニアやネットワークエンジニアなどいくつかの種類があります。
担当によって扱う業務はサーバーやネットワーク・セキュリティなどさまざまですが、いずれの仕事も要件定義から構築・運用・保守に分かれます。一般的にはITインフラの設計・構築を行い、正しく動作するのかをチェック・保守するのが主な業務です。
インフラエンジニアは、企業全体のシステムを担う際に安定して稼働できるように支える重要な職種といえます。
インフラエンジニアの主な仕事内容
次にインフラエンジニアの主な仕事内容を具体的にご紹介していきます。インフラエンジニアの仕事は細分化されており、ITシステムを稼働させる上で非常に重要な役割を担っています。
インフラエンジニアの主な仕事内容としては、要件定義から基本設計・構築・運用保守などといった幅広い領域を担当します。インフラが整備されていないと、システムが正しく稼働しないため、インフラエンジニアは重要な役割を担っています。
これから、インフラエンジニアを目指す方はどんな仕事をするのかしっかりと把握しましょう。ここからは、インフラエンジニアの主な仕事内容について詳しくご紹介していきます。
要件定義・非機能要件定義
要件定義とは、システムの導入目的やシステム要件を明確にして、インフラに必要な条件を洗い出す工程です。要件定義では、顧客との打ち合わせを通じて、「どのようなネットワークやサーバーが必要か」・「可能性や性能はどのレベルで必要か」などを明確にしていきます。
具体的にはクライアントのヒアリングを通じて現行システムの問題点や新しい要件を明確にし、それに基づいてシステムの性能・セキュリティ・スケーラビリティなどの要件を定義します。
システムの要件をまとめたら、結果をドキュメント化し、関係者全員と共有することで、プロジェクトの透明性を確保します。要件定義にはITの専門的な知識だけでなく、クライアントのビジネスプロセスを理解する力も求められます。
このプロセスを経て、次はクライアントの要件を満たすための具体的な設計と実装の準備を整えます。
基本設計
基本設計とは、要件定義で決定した内容を基に、システムの具体的な機能や構成を定義する段階です。このプロセスでは、サーバーの数やストレージ容量などの構成要素はもちろん、システムの信頼性・セキュリティ性などといった多岐に渡る技術的な要素を決めることが必要です。
具体的には、どのような構成・システム規模・設定値にするのが最適かなどの詳細を決定し、設計書を作成していきます。
設計段階では、将来的なシステムの拡張や変更に対応できる柔軟性も考慮されます。これはクライアントのビジネスが成長する中で、システムが適切に対応できるようにするためです。
基本設計は現場のルールや起こりうるトラブルおよび発生時の対処方法・準備として何が必要かなど、あらゆるシーンを想定した計画を立てることが求められます。
詳細設計(パラメータシート作成)
詳細設計とは、システム開発における工程の一つで、基本設計で決定した内容をさらに詳細に実装可能なレベルまで落とし込む設計です。詳細設計は基本設計で定めたシステム構築の方針や方式に沿って、具体的にどのようなパラメータ設定からミドルウェアおよび稼働設定をするのかを定めていきます。
例えば、システムの全体アーキテクチャ図などを含めることで、開発者がシステムの全体像を把握しやすくなります。
インフラ環境はアプリケーションを動かすための土台となるため、アプリケーション開発者が必要とする環境を実現する設計をしなければなりません。詳細設計はプログラミング担当者向けにシステム実装の方針を示すのが目的で、プログラムの構造・画面のレイアウトなどを含むのが特徴です。
そのため、詳細設計は、エンジニアやプログラマーなどの開発者側が中心となりプロジェクトを進めていきます。
構築
構築とは、設計が完了した後に設計書に基づいて実際に作り上げるプロセスです。構築段階に入ると、物理サーバーやネットワーク機器の設置・仮想マシンの設定からスタートし、OSのインストール設定までの実施が含まれます。
構築段階では、テストを実施してシステムが正しく動作するかを確認することも重要な業務です。テスト結果に基づいて必要な調整を行い、最終的にクライアントに引き渡します。業務では、クライアントの業務に支障が出ないよう、慎重かつ迅速に作業を進めることが求められます。
構築業務は、インフラエンジニアのスキルと経験が問われる場面で、しっかりとした基盤を築くことで、後の運用や保守がスムーズに進みます。
単体試験
単体試験とは、最初に個々のハードウェアやソフトウェアの動作や設定を単独で検証する作業を実施します。単体テストの主な目的は、クラウド環境の各リソースが詳細設計書の通りに正しく設定されていることを確認し、構築ミスや設定漏れを防ぐことです。
この試験では、最初に個々のハードウェアやソフトウェアの動作や設定を単独で検証する作業を実施します。例えば、Webシステムのフォームで、ユーザーが入力したデータが適切にデータベースに格納・保存されるかどうかを試験するといったことが一つ挙げられます。
特にクラウド環境ではリソースのパラメータが多数存在しているため、意図しない設定ミスが発生する可能性があります。そのため、単体試験を通じて仮想マシンのスペックやネットワーク設定・セキュリティ設定などが設計通りになっているかを検証し、問題を早期に発見することが重要です。
結合試験
結合試験とは、複数のプログラムやモジュール・コンポーネントを適切に連携し合い、不具合がないか検証する試験です。結合試験は、モジュール間の連携やデータの受け渡しなどに問題がないことを確認するのが目的です。
例えば、システムの挙動を確認するだけでなく、動作する機能と操作の組み合わせが適切かどうか、機能間の連携が仕様書に沿って正しく行われているかどうかなど、複数回にわたって確認します。
単体テストで実施しているテスト項目は、結合テストではほとんど行わないか、簡易的に確認するレベルに留めることが一般的です。結合テストは、システムの規模や対象のシステムによって、テスト内容が大きく変わります。
そのため、結合テストを実施する際は、単体テストの開始・終了時期を考慮して設定する必要があります。
運用・保守
運用・保守とは、システムの安定稼働を維持するために欠かせない、インフラエンジニアの重要な役割です。運用保守は、システムの安定性を確保するためを目的に監視やトラブルシューティングを行い、障害やエラーを迅速に解決します。
運用では、システムが24時間365日安定して稼働するように、ネットワークやサーバーの状態をリアルタイムで監視し、問題が発生した際には迅速に対処します。一方で保守は、システムが長期間にわたって安定して稼働し続けるために必要な修正や更新を行う活動を指します。
例えば、システムのメンテナンスやアップデート・セキュリティ対策が中心となります。運用・保守は技術の進化や外部環境の変化に伴い、システムの安定稼働を保証することが大切です。
運票が現状のシステムを最良の状態で維持することに焦点を当てるのに対し、保守は将来的な問題を未然に防ぎ、システムを進化させることに重点を置いています。
監視、障害対応
最後に監視・障害対応とは、サーバーやネットワークが障害などで停止しないように、システムのメンテナンスを行う職種です。システムの監視は、設計の中で行う監視設計の内容に基づき、システムを構築後リリースまでに監視設定を行います。
例えば、サーバーやネットワークスイッチなどが機器故障により異常が発生したとき、異常機器を速やかに検知し、対処しなくてはなりません。インフラはシステムの定期的なメンテナンスが必要で、故障の予兆がある部品は事前に交換計画を立ててメンテナンスをしていきます。
一方、障害対応とは、システムやサーバー・ネットワークに何らかの問題が発生した場合に、原因を調査から復旧させるための作業全体を指します。企業を支えるシステムは業務影響を最小限に抑え、障害が発生した場合は迅速に正しく行うことが求められます。
このため、予期せぬ障害に対応するためには、復旧に必要な情報を正確に収集し、障害時の対応手順をあらかじめ準備しておくことが重要です。
上流工程ほど単価がレベルも上がる
インフラエンジニアが上流工程で担当する具体的な業務としては、以下のようなものが挙げられます。
- 要件定義・非機能要件定義
- 基本設計
- 詳細設計(パラメータシート作成)
- 構築
- 単体試験
- 結合試験
- 運用・保守
- 監視、障害対応
上流工程は、要件定義から設計・監視・障害対応くらいまでが上流工程と呼ばれます。インフラエンジニアは上に行くほど、求められる知識レベルも高くて給料も高く、難しい仕事を担当することができます。
フリーランスのインフラエンジニア案件の月額単価は、実務経験により単価が異なります。実務経験1〜2年の週5常駐案件における単価相場は、月単価30万円〜55万円ほどです。実務経験が1〜2年程度のインフラエンジニアであれば、運用・保守などの下流工程案件が中心となります。
始めは障害やトラブルの下は、ハードウェアなどの故障から人為的な操作ミスなどといったパターン性があり、求められる知識や経験が多くないため、その分単価も低い傾向があります。
インフラエンジニアが使用するツールや技術

インフラエンジニアは、さまざまなツールや言語を駆使して業務を遂行します。特に実際のネットワーク機器やサーバーに接続して行う構築から運用・保守といったそれに伴う検査といったシーンでは、機器上の設定ファイルやネットワーク上の通信の状況・サーバーの監視を行うためにソフトウェアツールの活用が必須となります。
ここからは、インフラエンジニアが使用するツールや技術について詳しく解説していきます。
サーバーエンジニアが使用するツール・技術
サーバーエンジニアとは、システムを運用するためのサーバーを0からサーバー設計から構築・運用・障害対応を行うエンジニアです。近年、多くの企業が自動化を優先課題として挙げており、LinuxとAnsible・Zabbixはその戦略を支える一つのツールとなっています。
Linuxとは、オープンソースのUnix系OSで、サーバー向けのOSとして世界中で広く利用されています。このツールはだれでも無料で利用することができ、長期間にわたって再起動せずに稼働させることが可能です。
Linuxは高いハードウェア認識機能を持っており、パソコンなどのデバイスの構成を自動で認識できます。一方、Ansibleとは、サーバーをはじめとしたIT機器の管理作業を自動化する際に使うオープンソースの構成管理ツールです。
Ansibleは、構成管理ツールとして、シンプルな操作性と柔軟な拡張性を兼ね備えており、インフラ構築のコードの自動化に最適です。
さらに、Zabbixは統合監視ツールとして、システムの可視化やパフォーマンスの最適化を提供します。
インフラ構築は、これら3つを組み合わせることで、さらに運用全体の効率が高まります。
ネットワークエンジニアが使用するツール・技術
ネットワークエンジニアとは、企業や組織のネットワークシステムを設計から構築・運用・保守するITエンジニアのことです。業務でネットワークの設定変更や目視チェックなどといったさまざまな作業を行います。
エンジニアとしてはネットワーク自体の知識だけでなく、特定のツールを使うことで効率化したりミスを防いだりできます。
ネットワークエンジニアが使用するツールは、以下のように挙げられます。
・Cisco
・Network
・Monitor
まずCiscoは、ネットワーク機器業界で世界的に圧倒的なシェアと実績を持つアメリカのIT企業です。Ciscoのツールは、機器が搭載している機能を最大限に活かした管理が行える点が挙げられます。
一方、Networkとはネットワーク上のトラフィック、機器の状態、帯域使用状況などをリアルタイムに監視するためのソフトウェアです。Networkはどのアプリケーションや端末が帯域を使用しているのかを可視化することで、ボトルネックの原因分析ができます。
さらに、Monitorとは、ネットワーク上の通信状況やトラフィックの流れをリアルタイムで可視化・監視するためのツールです。Monitorはルーターやスイッチの状態をリアルタイムで可視化し、異常値が出た瞬間にアラートを送信することができます。
アプリケーションや端末が帯域を使用しているのかをトラフィック解析で、ボトルネックの原因分析ができます。このようにネットワークエンジニアは、システム障害が起きたときにこれらのツールを選ぶことにより、自動化を進めることができます。
データベースエンジニアが使用するツール・技術
データベースエンジニアとは、データベースの開発や設計から運用・管理を専門に担う技術者です。データベースは、企業の膨大なデータを保管しており、必要なデータを抽出・可視化するのに時間がかかってしまう場合があります。
そこで、データベースエンジニアに合ったツールを使用すると、データをスムーズに扱うことが可能です。例えば、MySQL / PostgreSQL、Oracle Databaseがその一つに挙げられます。
MySQLとは、オープンソースとして広く普及しているリレーショナルデータベース管理システムです。このツールは、オープンソースでWordPressやEC-CUBEなど多くのCMSと連携可能なのが特徴です。
オープンソースなため、大量のユーザーアクセスの処理を必要とする中小企業や大規模アプリケーションにおいて欠かせない存在となっています。一方、PostgreSQLはエンタープライズ向けの高機能・高信頼性を持つツールで、Oracle Databaseは高いパフォーマンスと可用性、セキュリティ機能を持ったツールです。
これらのツールは、複雑なトランザクション処理に強く、複雑な処理を実行することができます。このようにデータベースエンジニアで使用するツールは、業務や企業規模によって異なっています。
このため、それぞれのツールの強みをチェックすることが大切です。
セキュリティエンジニアが使用するツール・技術
セキュリティエンジニアとは、企業や組織の情報システムをサイバー攻撃や不正アクセスから守る職種です。セキュリティエンジニアは、システム障害やサイバー攻撃からシステムを守るために運用するのが特徴です。
セキュリティ環境は常に変化しており、新たな脆弱性が日々発見されています。定期的な診断が非常に重要ですが、手動での診断は人手・時間・コストがかかり実施が難しいことがあります。
そこで、SplunkとCheckovのツールを使用すると、リソースのデプロイ前に潜在的なセキュリティリスクを検出できます。Splunkは導入の低コストかつ複数のシステムのログデータを管理することが可能です。
一方、Checkovはツールで記述されたコードのセキュリティチェックを行うためのオープンソースツールです。Checkovはネットワークの設定ミスや暗号化の欠如といった問題を検出し、詳細な修正ガイドを提供します。
セキュリティエンジニアにおいて、Splunk は実運用環境の監視と対応に強みがあり、Checkov は開発段階でのセキュリティチェックに最適です。
クラウドエンジニアが使用するツール・技術
クラウドエンジニアとは、クラウドサービスを利用してITシステムの設計から実装・運用・保守を行うITエンジニアです。クラウドエンジニアは、インフラ設計だけでなくクラウド環境の構築し、運用することが特徴です。
しかし、自社のシステムがオンプレミス環境からクラウド移行したいときどのツールを選べばいいのか悩む方も多いはずです。そこで、クラウドエンジニアが使用する一つがAWS・Azure、GCPのその一つが挙げられます。
AWSとは、物理サーバーの設置や管理が不要で使用できる、Amazonが提供するツールです。AWSはインフラのコード化ツールとの親和性が高く、インフラ構成の自動化や再現性の確保に優れています。
一方、AzureはMicrosoft製品やオンプレミス環境との接続や連携を得意としていて、GCPは料金体系が比較的分かりやすく、必要に応じてリソースを拡張できるため、企業は常に最適な状態でシステムを運用することが可能になります。
インフラエンジニアに求められるスキル
インフラエンジニアは、企業やサービスの基盤となるシステムを支える上で重要な職種です。具体的には、サーバー構築やネットワークの設定・セキュリティ対策などといった運用・保守を担当します。
しかし、インフラエンジニアは技術の幅が広く、企業側がどのようなスキルが必要なのか気になる方が多いはずです。ここからは、インフラエンジニアに求められるスキルを具体的にご紹介していきます。
ExcelやWord、PowerPointでの資料作成スキル
インフラエンジニアを目指す上で大切なのは、ExcelやWord・PowerPointでの資料作成スキルが求められます。これらのスキルが必要な理由は、設計書や仕様書の作成・そしてプレゼンテーション資料の作成が挙げられます。
例えば、Wordを使った仕様書の作成では、表や図形を活用して情報を整理するスキルが求められます。また、Excelを使ったデータ分析やプロジェクト管理によって、プロジェクトの進捗状況やシステムの稼働状況を把握することが可能です。
Excelはフィルター機能を活用することでログデータを簡単に絞り込むことができ、Pivotテーブルを使えば大規模なデータセットから必要な統計情報を素早く取得できます。さらに、プロジェクトの進捗状況を社内外に報告する際には、PowerPointで視覚的に分かりやすい資料を作成することが求められます。
これにより、インフラエンジニアはプレゼン資料やプロジェクト管理シートを作成することで、ドキュメントの内容が理解しやすくなります。
最新技術に順応するスキル
インフラエンジニアは、クラウド移行に伴って最新技術に順応するスキルが求められます。近年、インフラエンジニアの中でクラウドの自動化やゼロトラスセキュリティの導入で新技術が次々と登場し、習得がますます重要になっています。
これに伴い、クラウド環境の基礎知識や自動化ツールの活用スキルがインフラエンジニアの必須条件となるでしょう。インフラエンジニアを長期的なキャリアで目指すためには、技術的なスキルだけでなく、最新技術に順応するスキルが求められます。
長期的に活躍するためには、他のエンジニアとのネットワーキングを通じたり最新のニュースを熟読し、新しい知見を得る習慣を身に付けることが大切です。
トラブルや障害に対応するスキル
インフラエンジニアに求められているスキルは、トラブルや障害に対応するスキルです。インフラエンジニアは、自社のシステムを安定的に稼働できるために重要な役割を担っています。
業務として活躍するためには、障害やセキュリティ侵害などのリスクを回避するのに常に高いレベルの集中力と対応力が必要です。また急なトラブルの対応が迅速に求められるため、その状況の中で的確な判断と対応をすることは業務的な負担を伴うことがあります。
そのため、トラブルに対応するスキルが高いと、プレッシャーの中でも冷静かつ確実に仕事を遂行できるため、周りに安心感や信頼感を与えるエンジニアになることができます。
まとめ
本記事では、インフラエンジニアの主な仕事内容について詳しくご紹介しました。インフラエンジニアは、企業や組織のインターネットを経由してインフラの設計から構築・運用を行う職種です。
現在の職種からインフラエンジニアを目指すには、サーバーやネットワークの専門知識だけでなく、障害が起きたときのトラブル対応も必要です。また、一度スキルを身に付けても技術の変化に合わせて勉強し続ける必要があります。
そのため、インフラエンジニアとして活躍するためには、基礎から実践レベル・トラブル対応を円滑に進めるためのコミュニケーションスキルを身に付けることが重要です。このようにインフラエンジニアは、ネットワークの専門スキルとコミュニケーション力を高めることで、幅広いキャリアパスも描くことが期待できます。