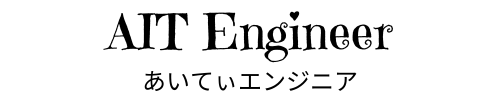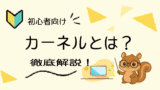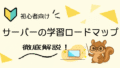インフラエンジニアを目指す際、サーバー、ネットワーク、データベース、セキュリティなどさまざまな知識が求められます。その中の一つであるサーバーの学習をする上で、まず理解すべきなのがOS(オペレーティングシステム)です。
OSは、サーバーやクラウド環境で動作するすべてのシステムの基盤となる重要な存在となっています。
本記事では、OSの基本概念から主な役割、構成要素、代表的な種類まで、初心者にも分かりやすく解説します。特に、インフラエンジニアが最も多く扱うLinux系OSについても詳しく紹介。
OSの知識を身につけて、インフラエンジニアとしての第一歩を踏み出しましょう。
OSとは?
OS(Operating System:オペレーティングシステム)とは、コンピューターのハードウェア(CPU、メモリ、ディスクなど)を管理し、アプリケーションソフトウェアが動作できる環境を提供するソフトウェアです。
コンピューターの電源を入れたときに最初に動き出し、ハードウェアとアプリケーションソフトウェアの間に立って、全体をコントロールする役割を担っています。
OSがなければ、普段使っているブラウザやメールソフトなどのアプリケーションは動きません。つまり、OSはコンピューターシステム全体の「司令塔」のような存在と言えるでしょう。
OSの主な役割
OSは、コンピューターシステム全体を効率的かつ安全に動作させるために、多くの重要な役割を担っています。これらの役割は大きく「ハードウェア管理」「ユーザーインターフェースの提供」「セキュリティ管理」の3つに分類できます。
特にインフラエンジニアにとって重要なのは「ハードウェア管理」の部分です。サーバーのCPU使用率やメモリ使用量を監視したり、ディスク容量を管理したりする際に、OSがどのようにこれらのリソースを制御しているかを理解していることが、適切なシステム運用につながります。
それぞれの役割について詳しく見ていきましょう。
ハードウェア管理
OSの最も重要な役割は、コンピュータのハードウェアを効率的に管理することです。
複数のアプリケーションが同時に動作する環境で、限られたリソースを適切に配分し、システム全体の安定性を保ちます。
サーバーのハードウェア(CPU・メモリ・ディスク)については、以下の記事で解説しています。
1. プロセス管理
プロセスを起動・終了させたり、CPUの時間をうまく分けてマルチタスクを実現します。高速で各プロセスを切り替えながら処理しているため、人間には同時に動いているように感じられます。
また、プロセスの優先度を設定して、重要な処理により多くのCPU時間を割り当てることも可能です。
2. メモリ管理
各アプリケーションに適切なメモリ領域を割り当て、他のアプリケーションのデータを破壊しないよう保護します。
また、物理メモリが不足した場合には、使用頻度の低いデータをディスクに一時的に退避させる「仮想メモリ」機能により、実際の物理メモリ容量以上のメモリ空間を提供します。
3. ファイルシステム管理
ハードディスクやSSDなどのストレージデバイス上のデータを、ファイルとディレクトリの階層構造として整理します。これにより、ユーザーやアプリケーションは、複雑な物理的なディスク構造を意識せずに、直感的にデータを扱うことができます。
4. デバイス管理
多種多様なハードウェアデバイスを、アプリケーションが統一的なインターフェースで利用できるようにします。
例えば、異なるメーカーのネットワークカードでも、アプリケーションからは同じ方法でアクセスできるよう抽象化を行います。
ユーザーインターフェースの提供
OSは、ユーザーがコンピューターを操作するためのインターフェースも提供します。コマンドラインインターフェース(CLI)やグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を通じて、ファイル操作、プログラムの実行、システム設定の変更などが可能になります。
セキュリティ管理
現代のOSは、不正アクセスや悪意のあるソフトウェアからシステムを保護するセキュリティ機能も備えています。ユーザー認証、ファイルアクセス権限の管理、プロセス間の分離などにより、システムの安全性を確保します。
OSとソフトウェアの違い
OSは「基盤」、アプリケーションは「その上で動く道具」という関係性があります。
OSは、コンピュータの基本的な動作を制御し、他のソフトウェアが動作するための基盤を提供します。システムの起動時に最初に読み込まれ、電源が切れるまで常に動作し続けます。ハードウェアリソースの管理や、セキュリティの確保など、システム全体に関わる重要な処理を担当します。
一方、ソフトウェアは、特定の目的のために作られたプログラムで、OSの上で動作します。Webブラウザ、データベースソフト、メールクライアントなどがこれに該当します。アプリケーションは、OSが提供する機能を利用してハードウェアにアクセスし、必要な処理を行います。
インフラエンジニアは、この基盤となるOSをしっかりと理解し、適切に設定・管理することで、その上で動作するアプリケーションのパフォーマンスと安定性を確保する役割を担います。
OSの構成要素
ここからはOSの構成要素について解説します。
| 構成要素 | 役割 | 具体例 | ハードウェアへの直接アクセス |
|---|---|---|---|
| ユーザー空間 | アプリケーションが動作する領域 | Webブラウザ、データベース、Webサーバー、ターミナル | ❌ 不可(安全のため) |
| システムコールインターフェース | ユーザー空間とカーネルの橋渡し | ファイル読み書き、ネットワーク通信の要求受付 | – |
| カーネル | OSの中核、ハードウェア制御 | プロセス管理、メモリ管理、デバイス制御 | ✅ 可能(特権モード) |
| ハードウェア | 物理的な機器 | CPU、メモリ、ディスク、ネットワークカード | – |
1. カーネル
カーネルは、OSの中核となる部分で、ハードウェアとソフトウェアの橋渡しを行います。プロセス管理、メモリ管理、ファイルシステム、デバイスドライバの制御など、システムの最も基本的で重要な機能を担当します。
カーネルは特権モードで動作し、ハードウェアリソースに直接アクセスできる唯一の存在です。これにより、システム全体の整合性とセキュリティが保たれます。
カーネルについて、詳細は以下の記事でも紹介しています。
2. ユーザー空間
ユーザー空間とは、普通のアプリケーション(Webブラウザ、データベース、Webサーバーなど)が動作するメモリ領域のことです。この領域で動作するアプリケーションは、安全上の理由から、ハードウェアに直接アクセスすることができません。ハードウェアを使いたい場合は、必ずカーネルにお願いする必要があります。
例えば、Webサーバーがファイルを読み込みたい時は、「ファイルを読んでください」とカーネルにお願いし、カーネルが代わりにディスクからファイルを読み込んで、結果をWebサーバーに渡します。
この仕組みにより、もしアプリケーションにバグがあって暴走しても、システム全体が壊れることを防げます。さらに、システムの安定性とセキュリティも向上させています。
インフラエンジニアが管理するWebサーバーやデータベースサーバーなどのミドルウェアも、このユーザー空間で動作します。
3. システムコールインターフェース
システムコールは、ユーザー空間のプログラムがカーネルの機能を利用するための仕組みです。ファイルの読み書き、ネットワーク通信、プロセスの生成など、ハードウェアリソースを使用する処理は、すべてシステムコールを通じて行われます。
プログラムがシステムコールを呼び出すと、CPUは一時的に特権モードに切り替わり、カーネルが要求された処理を実行します。処理が完了すると、再びユーザーモードに戻ります。この仕組みにより、セキュリティを保ちながら柔軟なシステム利用が可能になります。
4. ドライバ
ドライバは、特定のハードウェアデバイスを制御するためのソフトウェアです。ネットワークカード、ディスクドライブ、グラフィックカードなど、各種ハードウェアがOSから利用できるよう、デバイス固有の制御方法をOSに教える役割を担います。
現代のOSでは、多くの一般的なデバイス用ドライバが標準で組み込まれているため、新しいハードウェアを接続しても自動的に認識・利用できることが多くなっています。
インフラエンジニアとしては、サーバー用の特殊なハードウェアや、パフォーマンスを最適化するために専用ドライバが必要な場合に、ドライバの知識が重要になります。
OSの代表的な種類
インフラエンジニアは特にLinuxを中心に扱うことが多いです。なぜなら、クラウドやデータセンターのサーバはほとんどLinuxで動いているからです。
1. Linux系
サーバで最もよく使われる。Ubuntu, CentOS, Debian, Red Hat など。
Linux系OSは、エンタープライズサーバー市場で圧倒的なシェアを誇ります。オープンソースであるため無料で利用でき、ソースコードが公開されているため透明性が高く、セキュリティホールの発見・修正が迅速に行われます。また、軽量で高性能な特徴があり、サーバー用途に最適化されています。
主要なディストリビューションとしては、Ubuntu(使いやすさを重視し、デスクトップからサーバーまで幅広く利用)、CentOS(Red Hat Enterprise Linuxと互換性があり、企業サーバーで人気)、Debian(安定性を重視した保守的なディストリビューション)、Red Hat Enterprise Linux(商用サポートが充実した企業向けディストリビューション)などがあります。
2. Windows系
デスクトップや一部のサーバ用途。GUIに強い。
Windows系OSは、デスクトップ市場では依然として最大のシェアを持っています。直感的なGUI操作、豊富なアプリケーションソフトウェア、Microsoft製品との親和性の高さが特徴です。サーバー用途では、Active DirectoryによるWindows環境の統合管理、.NET FrameworkやSQL Serverなどとの連携に優れています。
ただし、ライセンス費用が必要で、Linuxと比較するとカスタマイズ性は限定的です。インフラエンジニアとしては、企業の既存システムがWindows環境の場合や、Microsoft製品中心のシステム構成を担当する場合に知識が必要になります。
3. Unix系
古くからあるOS。macOSも内部はUnix系。
Unix系OSは、1970年代に開発された歴史あるOSファミリーです。現在でも、高い信頼性と安定性を要求される金融系システムや基幹システムで利用されています。主要なUnix系OSには、Solaris(Oracle)、AIX(IBM)、HP-UX(HP)などがあります。
また、macOSもUnix系OSの一つで、BSD Unixをベースとしています。多くのUnix系OSは商用製品であり、専用ハードウェアとセットで提供されることが多いのが特徴です。
4. モバイル系
Android(Linuxベース)、iOS(Unixベース)。
モバイル端末向けのOSも、インフラエンジニアにとって重要な知識分野となっています。AndroidはLinuxカーネルをベースとしており、JavaやKotlinで開発されたアプリケーションが動作します。iOSはXNUカーネル(BSD Unix系)を使用し、Objective-CやSwiftで開発されたアプリケーションが動作します。
モバイルアプリケーションのバックエンドシステム構築や、モバイル向けAPIサーバーの運用において、これらのOSの特性を理解していることが重要になります。また、IoTデバイスでも軽量版のLinuxやAndroidが使用されることが多く、インフラエンジニアの業務範囲は拡大しています。
まとめ
OS(オペレーティングシステム)は、コンピューターシステムの基盤となる重要なソフトウェアです。ハードウェア管理、ユーザーインターフェース提供、セキュリティ管理などの役割を担い、その上でアプリケーションソフトウェアが動作します。
インフラエンジニアを目指す方にとって、特に重要なのはLinux系OSの知識です。現代のクラウド環境やデータセンターの大部分でLinuxが使用されているため、Linuxの基本的な操作、設定、トラブルシューティング能力は必須スキルと言えるでしょう。
また、OSの構成要素(カーネル、ユーザー空間、システムコール、ドライバ)の理解は、システムのパフォーマンス最適化や障害解析において重要な知識となります。まずはLinux系OSから学習を始めて、コマンドライン操作やシステム設定に慣れることをお勧めします。
OSの基礎知識をしっかりと身につけることで、インフラエンジニアとしての成長の土台を築くことができるでしょう。